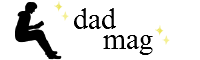しつけに体罰や叱責が必要ない理由とは

学校や教育に関する問題でしばしばテーマになるのが「体罰」の有無についてです。
特に高校野球の季節になると、その指導法についてどこまでの厳しさが許容されるべきかということが議論になったりします。
体罰は教育行為であるものの、一方で体格や社会的立場が高い大人が子供に対して行う暴力行為であるということには代わりがありません。
一昔前までは先生や親が子供を日常的に叩くようなことも当たり前に行われてきましたが、現在ではそうした暴力的行為を伴う教育方法は全く意味がないばかりか害となることがわかっているので、仮にどのような事情があるとしても一般的には許容されないものというのが常識です。
暴力行為は直接的に身体に傷害を追わせるものであるため、場合によっては大きなケガをしてしまったり、エスカレートしてしまうことにより障害として体に残ってしまうこともあります。
そうしたこともあってようやく世間的には暴力を伴う体罰は減少傾向が見られるようになってきましたが、一方で直接的な暴力を伴わない体罰については水面下で広がってきているようです。
いわゆる「言葉の暴力」ですが、これは一見直接的に傷害を負わせない代わりに心に一生残る傷を負わせてしまう危険性があります。
教育現場だけでなく家庭生活における体罰も同じようなもので、子供のためと言い訳をしつつ怒鳴ったり時に手を上げてしまったりするとことは、教育面においては非常によくない影響を与えてしまうことになります。
萎縮してしまうことによる生育への悪影響
もちろん、子供の教育のために怒鳴ったり手を上げたりするということが完全に悪で絶対にやってはいけない犯罪行為であるというわけではありません。
他人の身体に大きなキズや損害を与えるような悪質な行為をしていたり、自分自身を大切にしないような行為をしている子供に対しては時に厳しくそのことを教える必要があるからです。
ただしそうした厳しさも、普段の優しさとのギャップがあってこそ成り立つものであるので、常に誰かを怒鳴ったり殴ったりしているような人の場合、その体罰が正当化されることは全くありません。
暴力や恫喝によって子供をしつけた場合、子供はそうされることを極端に恐れるようになるので、自分の意思でリスクととった挑戦をしなくなります。
またミスや誤りが発覚してしまうことでイヤな思いをするので、そうした重大なインシデントがあっても報告をすることなく自分の中だけに隠しておくような行動をとるようになります。
それ以上に問題なのは正しく対等なコミュニケーションをとることができなくなるということで、将来友達や恋人として付き合う相手にも恫喝や暴力を好む人を選ぶようになる傾向があります。